|
Richard Cantillon 1680?-1734 スペイン名を持ち、フランスに住んで、ジョン・ローの手口で 2 千万リーブルを儲けてイギリスに移住した。アイルランド人カンティリョンは、ロンドンの自宅の火災で死亡する。 1732 年頃に彼がフランス語で書いた「Essai」 は、死後 20 年してイギリスで刊行された 。フランスではよく知られていたが、英語圏では1880 年代になって再評価される。 「経済」を市場の集合とし、それらが価格システムで結ばれ、バランスのとれた循環フローが存在している、というビジョンを提示した。さらに、「価値」を「土地価値説」とし、完全なモデルを定義している。 生産要素は二つ(土地と労働)で、財は二種類(必需品と贅沢品)とする。結果として、4 つの市場ができ、価格も 4 種類出てくる。 人には二種類あり、地主と労働者だ。
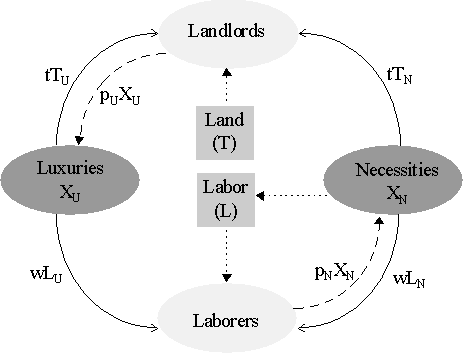 このような関係で、地主と労働者の間に所得と支出の循環的なフローがあると考えた。実線は所得、破線が支出。 直感的に、所得、支出、労働供給が「バランス」しないと、この経済単位が崩壊する。たとえば、労働者が必需品を買う十分な賃金をもらえなかったら、飢え死にする。すると、労働を投入し必要な財が生産されなくなり、地主も贅沢品を買えなくなってしまう。 土地の総量 T は決まっているとする。ある国の食料生産に使える面積は限られているという前提で議論する。 一方、総雇用 L はどうだろう。カンティリョンは、「無限の生活資源があったら、人々は納屋のネズミのように果てしなく増殖する」と見た。生産される必需品の量 XN が、この経済単位の養える労働の総量 L を決めると予測した。 労働と土地の総需要を L(労働) = LN + LU と T(土地) = TN + TU としよう。 利益はなしとする。ある状態が維持できればいいとしよう。 総収入と総コストが等しいということになる。 総収入は、単純にそれぞれの財の生産量と値段のかけ算だ。一方の総コストは、財の生産で使われる労働と土地に、それぞれ賃金と地代のかけ算だ。数式で書けば、 pNXN=wLN +tTN (1) pUXU=wLU +tTU (2) ここでpN ,pU はそれぞれ、必需品と贅沢品の単価 w、t は労働の賃金単価と土地の地代単価 この系が長期的にバランスするなら、必要な労働量を維持するのに十分な必需品が生産されなきゃいけない。 これは、賃金総額が必需品を買えるだけの金額でないとダメ。つまり pNXN=wL=wLN+wLU (0) となる。式(1)と比較すれば、 tTN=wLU 式(2)に代入すれば、 pUXU=tTN+tTU 地主が消費する総額は、きっちり地代だけ。当然の話。 労働者は均質としよう。c=XN/L は、一人の労働者の必需品の量という意味になる。 式(0)より、 w/pN=XN/L=c つまり w=cpN これは、一人の労働者が必需品を買う収入が賃金ということを意味する。これが所得フローを維持するメカニズムである。 さて、この条件で、他の価格も決まり、土地Tによってすべての価格が決定される。土地が市場を決める源泉。カンティリョンは、「土地価値説」を唱えた。 数値モデルで「土地価値説」を表現する前に、準備として「技術」を定義する。 XNを作るのに必要な労働を、次ぎのように表現してみる。 LN=αLNXN 同じように、XNを作るのに必要な土地は TN=αTNXN 贅沢品についても LU=αLUXU TU=αTUXU 例えば、αTUは1単位の贅沢品を作るために必要な土地(単位投入量)という意味。 耕作技術が進歩すると、少しの土地で1単位の贅沢品を作ることができるようになる。土壌改良であったり、品種改良であったりする。これは、その時点の「技術」といえる。ここでは、「技術」は決まっているとして議論を進める。 式(1)に単位投入量を代入すると、 pN=wαLN +tαTN (1’) w=cpNを代入して、 pN=cpNαLN +tαTN (1’’) 結局、 pN=tαTN/(1-cαLN ) 同様に、 pU=(cαLUtαTN/(1-cαLN )) + tαTU w=ctαTN/(1-cαLN ) これで、地代 t を基準として、他の3つの価格が決まる。 カンティリョンは、土地 T と、そこに住む労働者一人当たりの必需品の量 c と、生産「技術」によって、すべての価格が決まることを示した。 結論から遡ると、 L=αLUT/(αTU + cαTN αTU (αLU/αTU-αLN/αTN )) で、その土地に投入する労働量が決まる。 地主は地代 t を提示して、賃金 w を約束する。 w=ctαTN/(1-cαLN ) 労働によって無事収穫される必需品と贅沢品に相当する量は、 XN=cαLUT/(αTU + cαTN αTU (αLU/αTU-αLN/αTN )) XU=(1-cαLU)T/(αTU + cαTN αTU (αLU/αTU-αLN/αTN )) 一旦、 XNとXUに相当する収穫物は市場に出され、 tTとwLの収入を得る。tTは地主、wLは労働者に分配される。 労働者は、賃金すべてを生きるための必需品に消費する、その物価は pN=tαTN/(1-cαLN ) 地主は、生産に直接タッチせず収入を得て、消費する。その意味で、贅沢品と呼ぶが、その物価は pU=(cαLUtαTN/(1-cαLN )) + tαTU 地代 t により、賃金w、物価pN、pUが決まる。四つの市場の価格が地代 t の比率で確定する。具体的な金額は時代やそれぞれの国の物価水準で決まる。物の「価値」は、何かを基準にして相対比率がきまれば、それでいい訳だ。小麦とりんごを交換する時に、一旦「金」に換算して交換する。それが貨幣経済の知恵である。合理的な交換尺度を決めることが経済学の「価値理論」。 カンティリョンは、経済学の最も基本となる、財の「価値」は、地代 t 、結局は、土地 T で決まると代数学で表現してみせた。 この「土地価値説」は、フランス革命前のフランスで唱えられた。すでに十字軍の11世紀にフランス農業は荒地を開拓する時代は過ぎていた、商業も発達していた。あくまでも、穀物生産を主体とする農業国フランスの事情を整理したものである。 地主と農民(労働者)の経済単位があり、主に小麦を生産する大多数の集団と、例えば、塩、乳製品、ブドウを生産する集団が商人によってリンクされると考えてみよう。 塩に特化した集団の商品「塩」の価格は、「小麦」を生産する集団の必需品価格とリンクして決まってくる。乳製品もブドウ酒も同様。 こうして、所得と支出の循環的なフローがある経済単位の商品(財)リンクにより社会の経済が成り立っていることをと明示した意義は大きい。 当時のフランスは啓蒙主義の時代。自然科学の原理のようなルールが経済にもあるはずだと考えた。自然の摂理には逆らえないように、原理に基づく経済活動が真理で、それが「自然状態」なんだとする社会風潮だった。ケネーは、表形式の「経済表」でフローの説明を試みている。カンティリョンは数理経済学の元祖として代数を使った。 りんご三つ、ミカン三つから「3」という数を抽象化する。これが数学というもの。3、5、9といった数字から変数Aを抽象する。これが代数学。このような思考能力は、物物交換を貨幣尺度で合理的にする商人、特にに異国間の交易をしたアラビア文化で発展した。 スペイン名を持つカンティリョンが、数理経済学の元祖ということに、妙に納得するのである。 カンティリョンは、「価値」と「価格」はちがうよとも言っている。市場で今日決まったリンゴの「価格」は、今日の需要と供給で折り合いがついた値段。その日によって変動する。でも、長期的に「自然状態」で落ち着く理論値があるはずだ。それがりんごの「価値」。それを知るには、こんな代数学で整理できる経済モデルが無くちゃいけないよと明示してくれた。1732年の「Essai」は文化遺産といえる。 |